2008.03.25
vol.8「ブラジル」
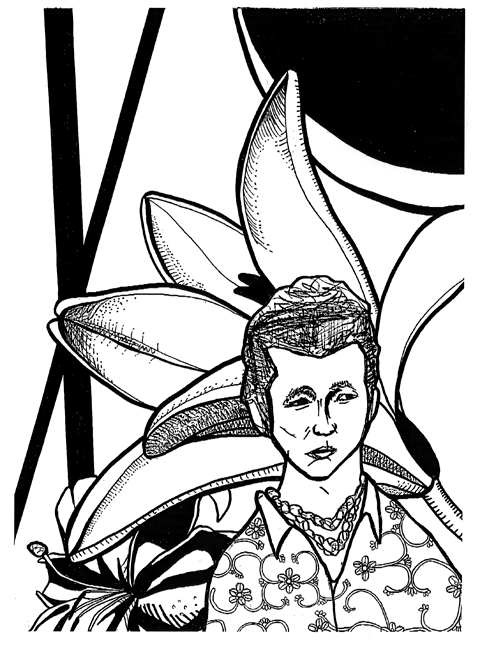
数ヶ月間の生活を東京で過ごしたぼくの目に、故郷山形は小さく寂しく映った。久しぶりに行った山形美術館にある印象派の油絵も、中学生の頃に受けた衝撃と輝きはなかった。
中学生の頃に観た、山形美術館の白い壁に掛かった印象派の油絵……。その作品の前に立った瞬間、目の前に現れた扉が、ギィーと、音をたてて開き、扉の向こうへ踏み込めば、突如としてぼくは19世紀末のフランスの大地に立ち、画家の見た光景を眺め、風や匂いを感じることが出来た。
しかし、いま目の前にあるのは73.0×100.0センチの額に収まった色のついたキャンバスでしかない。
美術館の大窓から、通りを歩く人々が見える。日傘をさして歩く女性。ネクタイを緩め、うちわをあおぐ男性。水鉄砲を持った小さな男の子が女の子を追いかける。
昼間の強い日差しが容赦なく降り注ぐ。
一世紀もの間、絵の具は画家の見たままの光景を形成し続け、数えきれないほどたくさんの人々の心を揺さぶった。
変わったのはぼく自身だった。
ぼくは、東京で何よりも刺激的なものをこの目で観たんだ…。
冷房機の呼吸する音が聞こえるほど静かな美術館の中で、ぼくは、東京でひとり暮らしをしている自分に陶酔した。
夕方、実家の縁側に座り、一日の勤めを終えて地平線に沈もうとする真っ赤な太陽を眺めながら、甘い夏の香りがするスイカにかぶりついた。
蝉の鳴き声……。
庭のよく手入れされた松の木にしがみつき、昼間以上に大きな音で鳴いている。
遠くに見える竜山……。
ふと、ぼくが通った南小学校の校歌を思い出した。
茜さす峰 竜山の
萌える緑に 朝開く
真白き学園(その)は 照り映えて
やさしい心 若竹の
校章(しるし)輝く 南小学校
台所でまる茄子の漬けものを作る母との会話が弾んだ。
仕事からいつもより早く帰った父と兄も加わり、久しぶりに揃った家族の会話が活気づく。
ぼくはそれぞれに学校のことや寮での生活、食事、満員電車、新宿や渋谷の街のこと、さらには豆をよく買うコーヒーショップのことなど、東京での暮らしぶりを夢中になって話した。
東京でのひとり暮らしが、どれだけ自分のためになっているかを、都合がいい部分だけ厳選して話した。
今までこんなに自分のことを家族に話したことはなかったが、ここが自分の生活の拠点でなくなったぼくは、たまに顔を出すお喋り好きの親戚のような調子で話し続けた。
父と母は無事に故郷へ帰ってきた息子と家族揃って夕飯を食べれることを心から喜んでいた。しかし、父と母は、東京でのひとり暮らしをこんなにも喜んで報告する息子を見て、内心どう思っていたのだろうか…。
ゆったりと実家の湯舟につかっているとき、ついこの間まで髪を金髪にしてライヴハウスへ入り浸っていた自分が不思議に思えた。いま実家で悠々と風呂につかっている自分と東京での自分、なんだか妙な違和感があったが、風呂上がりに食べた母ちゃんの手料理をうまいうまいと食べ始めたころには忘れていた。
数日後、「東京の変なひとには着いて行くなよ。はんこは簡単に押すなよ。ちゃんとしたご飯を食べて、体だけは大事にしなさいよ。」と別れ際に言った母に手を振り、父の運転する車で実家を出た。
父に見送られ、山形新幹線つばさに乗って東京へ向かう。
窓側の席に座る。出発してすぐ、上山辺りで気高くそびえ立つ蔵王や竜山が見えた。
白龍湖が見えてきた。赤湯に入った。
白龍湖の上空で、まるで宙をひらひらと舞う花びらのように、悠々と風に乗ったハンググライダーを楽しむ人々。
高畠を過ぎ、新幹線はさらにスピードを上げる。
米沢を過ぎ、眼下にある渓谷を眺め、たくさんのトンネルを抜け、福島県へ入る。
スライドする景色を眺めながら、東京に近づくにつれて心拍数が上がり始める自分に気がつく。
期待に胸が膨らむ。
いつもより時間の経過がゆっくりと感じられ、東京までの2時間45分が長かった。
タバコに火をつける。
田んぼがビルへ、木々が電柱へと変わり、山形にいた自分が色褪せはじめる。
東京に入った。
タバコの白い煙が窓から見える東京の街をぼやけさせた。
自分になにが出来るかではなく、自分の身にこれからなにが起こるのかを夢想した。
ぼくは東京に戻ってすぐにまた髪を脱色し、金髪にして、ついでに右の眉にボディピアスをつけた。
そして求人誌で見つけた高級クラブのボーイとしてバイトを始めた。時給は1000円で高級クラブという割には安いと思ったが、東京の夜の仕事というのと、場所が銀座というところが気にいった。
ぼくの他にも同い年くらいの若者が三人ほど面接に来ていたが、面接をしてくれた野村さんから後から聞いた話によると、一番真面目に働きそうだったから、という理由でぼくが選ばれた。
実際ぼくは、店で働くたくさんの夜の女神たちにわき目もふらず真面目に働いた。
店を仕切るママさんは黒服(ボーイ)と呼ばれる男性従業員の中でも、特にウェイターと女神たちの接触を固く禁じ、仕事以外の会話をしようものなら、そのときはウェイターの給料を半分も減らした。もし店外で接触すればそのウェイターは即刻クビだ。
黒服のなかで会話を許されているのはマネージャークラスのひと達。
入ったばかりのぼくに仕事を教えてくれたチーフマネージャーである野村さんは、女神たちからも人気で、ママさんからの信頼も厚かった。
銀座から新橋方面へ中央通りを歩き、みゆき通りを右に曲がったところにあるビルの三階に、ママさんのお店はあった。
ぼくは、大通りではなく、生活臭のする裏通りを歩いたり、遠回りしてたくさんの画廊が並ぶ道を歩いてお店に通うのが好きだった。
ぼくたち黒服は、女神たちが店に入る2時間前の夕方5時にお店に入る。
まず店内の掃除をしてテーブルをセットする。それが終わるとフロアに集合し、黒服全員で声を張り上げお店の標語を読み上げる。そうしている間に女神たちが続々と店に入り、メイクをして着替える。
夜8時前に女神たちと一緒に全体朝礼。
いよいよ開店。
お店の入り口には、着物を着たママさんが、受付の前で背筋を真っ直ぐに伸ばして椅子に座っており、お客さんが来店すると、すっと立ち上がって「いらっしゃいませ。」と上品な声でお客さんを迎える。その一言で、ウェイターたちは「いらっしゃいませぃ!!!!」と声を張り上げ、チャイナドレスを着たエスコート専門の女神が、お客さんを席まで案内する。
そして、バーカウンタースペースで待機していた女神たちが、次々とお客さんの席へと旅立つ。
30畳ほどのフロアと6畳ほどのバーカウンタースペースは、受付のある廊下から左手と右手に別れており、チャイナドレスがお客さんを席に案内している間に、ママさんは預かったコートやカバンなどをロッカーに閉まった。
銀座の高級クラブというだけあって、シャンデリアや金細工が埋め込まれたテーブル、重量感のある坪に入った蘭の花、その他様々な装飾品に彩られた店内は高級感に溢れていた。
コンビニで買ったポテトチップスが、この高級クラブのケーキ皿大のお皿に乗ると、3000円のポテトチップスに変身した。
お会計は全てママさんが仕切っていたので、ぼくには検討もつかなかったが、学生のぼくには信じられないほどの額が毎日動いていたことだろう。
来店するお客さんは立派なスーツを着てくる人がほとんどだったが、同伴で入店するお客さんは、ハンドバック片手にポロシャツの襟を立ててくる人が多かった。
3000円のポテトチップスをおかわりする人たちだ、ぼくの想像を遥かに超えた大金持ちなんだろう……。
彼らは凜とした表情でソファーにでんと腰をかけると、まずタバコを口に加える。
女神は隣の席に座り、すかさずお客さんのタバコに火をつけ、自己紹介をする。
「お願いしまぁす」
女神に呼ばれたウェイターは、店にキープしてあるウィスキーや焼酎ボトル、それと水と氷を持って行き、グラスとお店の名前がプリントされたコースターをテーブルにセットした。
女神に酒をついでもらい、姿勢を正し、胸を張ってグラスを勢いよく口へ運ぶお客さんの姿は、まるで勝ち戦から帰ったばかりの勇敢な武将のようだ。
そして一時間後には背中は大きく曲がり、武将たちは体を女神に預けてヨロヨロと酒を呑み、鎧を脱ぎ始める。
袖を肩までまくり上げ、靴を脱ぎ、靴下さえも脱ぎ捨てているお客さんや、ハイになって誰にでもなく奇声を発するお客さん、大声で連れに説教を始めるお客さんはざらにいた。なかには「お前も座れ!!」とウェイターに絡んでくるお客さんもいた。ぼくもその標的となり「なんなんだお前のその顔は!! そんなとこにピアスなんかつけやがって!! 見苦しいから外せぇー!!!!」とその場でピアスを外したこともあった。
時間が経てば経つほどお客さんの顔の表情は緩み、笑い声は大きくなった。
しかし、会計を済ませ、女神に見送られて下りのエレベーターに乗るときには凜とした表情に戻っており、ドアが閉まり出すと、ママさんや女神、そしてぼくたちにまで真顔で「ありがとう」と言った。
身も心も解放して、酒と女神に囲まれた竜宮城でのひとときをめいいっぱい楽しみ、また外の世界へ帰っていく。
そんな大金持ちのおじさん達が、ぼくの目には気持ちのいい男として映った。
右も左もわからないぼくだったが、華やかな夜の世界を垣間見れたことに、密かに喜びを感じていた。
それに、なにせこのお店にいる女性は「女神」と呼ぶに相応しい女性ばかりで、どれも神話になりうるほどの美女が揃っていた。その美女が色とりどりのタイトなドレスに身を包み、上品な笑みを浮かべながら下品な親父に酒を注いでいるんだからたまらない。
これもバイトを始めてからしばらく経って野村さんに聞いたことだが、彼女たちの何人かはタレントのたまごで、なかにはすでにテレビに出ている子もいるという。
華やかだ。なんて華やかな世界だ。
そんな女神たちと、ぼくのような田舎のちょいワキガ持ちの小僧が同じ空間で仕事をしている、と思うと股間が熱くなった。
女神たちは仕事中も、お客さんを見送ったあとも、ひとりとして嫌な顔ひとつ見せず、ここでの時間を過ごしていた。
女神たちは仕事を楽しんでいた。
そんな女神と、開店前も閉店後も友達のように接するママさん。店内で流すBGMは、更衣室にストックしてある女の子たちの自前のCDの中から女の子とママさんとで選んだものを流していて、ママさんお気に入りのマドンナの曲が店内に流れると、女の子と一緒になって楽しそうにメロディーを口ずさんでいた。更衣室からは、女の子とママさんの賑やかな会話がいつも聞こえていた。
そのママさんから、一度だけ買い出しを頼まれたことがあった。
食器用洗剤とトイレ用洗剤、トイレットペーパーに、更衣室で女の子が読むファッション誌やダイエット本、料理本、旅行雑誌。
ぼくは、それらを忘れないように紙になぐり書きした。
「それと、占いの本も買ってきてちょうだい。んー、……夢占いがいいわね。女の子が喜びそうなやつね。」
頼まれたものを一式買い揃え、最後に、書店の棚に並んだ何冊かの夢占いの本に目を通し、時間をかけて一冊選んだ。
店に戻り、ビルの一階でエレベーターを待っていると、後ろから出勤したばかりの女の子が
「お疲れ様ですぅ」
と声をかけてきた。
「あ…どうもです…」
ぼくが右手に持っていた夢占いの本に気づくとその子は
「夢占い……、お店用ですか!?」
と喜び、無邪気に昨日みた馬の夢のことを話した。ぼくはその子と目を合わせられず、ふたりっきりのエレベーターの中でとっさに「馬」のページを探した。
エレベーターを降り、更衣室の前でぼくは「馬は精神的、肉体的な活力を表す、エネルギーの象徴です。また性的欲望や衝動を示します。白い馬の場合は〜」と本に書かれた文章を読み上げ、興味深く聞き入っていたその子に本を預けた。
そして、フロアへ向かおうと体の向きを変えると、獲物を見つけた猛獣のような目をしたママさんが目の前に立ちはだかっていた。
閉店後、お店のルールを破ったぼくは、ウェイターを仕切る野村さんと共に初めてママさんにこっぴどく怒鳴られた。
野村さんのおかげでぼくの給料には影響がなかったものの、まるで数年に一度の大嵐、強い風と大粒の雨、耳をつんざくような雷の音を体験した。
次の日、ママさんは何事もなかったようにぼくに接したが、野村さんは次にぼくが出勤するときに外で話をしよう、とぼくをお茶に誘った。
後日、出勤前に銀座のソニービル前で野村さんと待ち合わせをした。先に着いていたぼくが挨拶をすると、野村さんは「じゃ行くか」と、足を止めようともせずに続けて歩を進めた。
一言も話さず黙々と歩く野村さん。
ひとを見た目で判断するのはよくないが、角刈りで目つきがするどく、高級時計を腕にまき、素肌の上に着たブランドものの派手なシャツを胸元まであけて、金のネックレスをこれでもかと覗かせながら風をきって歩く野村さんは、誰が見てもその筋の人にしか見えない。
どこへ向かおうとしているのかもわからず、ぼくは下を向きながら、わずかに視野に入る野村さんの後ろ足を追いかけた。
しばらく歩いたところで、レトロな建物の入り口から延びた階段を上がっていく。
香ばしいコーヒーの香りが鼻を通り肺の中を満たした。
席に着くなりアイスコーヒーを注文する野村さん。ぼくも同じものを注文する。
「ママさん怒ると怖いだろー。でもお前良かったなぁ、初めてもらう給料、半分になるとこだったぞぉ。あれ!?お前店に来てからどんくらい経つっけ?」
!!!?
ぼくはつい野村さんにこっぴどく叱られるとばかり思っていたから、野村さんの明るいトーンの声を聞いて拍子抜けした。
「えっと……、ちょうど1ヶ月になります」
「そっかー。もうだいたい覚えたろ、仕事。どうだ!? きついか?」
きついことなんか一つもない。
「ママさん、女の子と話すのだけは許さねえ人だから気をつけろよ。前に、ウェイターとくっついた女の子が辞めてったりしたことあっからさ……。男が辞めさせるわけよ、男に酒ついでヘラヘラ笑ってんじゃねぇって。酒ついでる女に惚れたくせにそういうこと言うからよ。結構いたんだよ、そうやって辞めてく女の子」
「はい……」
こんなに喋る野村さんは始めてみた。
「村井、今18だろ!? 俺もさ、お前くらいのときに東京出てきてさ…。地元の族と手切って女とこっち出てきて、そいつのヒモになって、そりゃあもう、だらしねえ生活してたんだけど…。あるとき金が必要になってさ」
「族…ですか……」
「特攻隊長やってたんだよ。信じられねーか!?」
信じられた。薄々感じてはいた…。
当時付き合っていた彼女と静岡から上京し、一年間のヒモ暮らし後に、先輩の紹介でキャバクラで働くことになった野村さん。「根がだらしない」「もめ事が大好き」な野村さんが縦社会に馴染めず、他の従業員を怪我させクビになり、夜のお店を転々としたあげく、彼女にもふられ、身も心もズタズタになったところで今のママさんのお店に拾ってもらった……。
「俺、ママには感謝してんだ…」
「……。」
「……ママさ、俺らよりもだいぶ早く店に来てるの知ってるか!?毎日花瓶の水を替えてさ、枯れた花と買ってきたばっかの新しい花を交換するんだよ。みんなが気持ちよく働けるようにって」
入り口やトイレ、バーカウンター、ソファーの後ろの花瓶や、フロアの真ん中に堂々と腰を下ろしている大きな壺に、百合や蘭、薔薇などの切り花が添えられ、華やかな店内をいっそう華やかに彩り、各テーブルにある小さな花瓶に差した、茎を短く切ったガーベラが見る者を優しい気持ちにさせた。
女神たちは入店するなり、フロアに広がる花の香りに喜んだ。
従業員みんなからの人望が厚いママさん。その理由が少しわかった気がした。ママさんはお客さんと従業員を大事にし、自分のお店を愛していた。
「女手ひとつで店きりもりしてさ、息子さんも立派に育ててさ。息子さん、銀座で寿司屋経営してんだよ、すげーだろ!? 何回かママに彼女と一緒に連れてってもらったけどさ、旨いんだよ」
「野村さん……。彼女さん……、いるんすか!?」
「言ってないっけ? 店の奥でカクテル作ってる子、俺の女なんだよ。」
お客さんの中でも選ばれたひとしか座れないカウンターバーの席。そのカウンターバーで神秘のカクテルを作っている女神……。女神の中でも指折りの美女である。その美女の衣装だけはなぜかビキニで、ひいきにしているお客さんなのか、ママさんの知人なのか、どちらにせよ、特別な人だけが両脇に女の子を座らせ、そのカクテルを呑むことができるのだ。
ああ、なんてことだー!!!!
あんた、店の女の子と付き合ってるんじゃないかぁー!!
偽善者め!!
ママも黙認してるのかっ!?
てめぇー、ママとヤッただろー!?
このイカ野郎!!
さてはママの店を乗っ取るって魂胆だなっー!!
野村めっ、信じられん!!
そもそも金髪で眉にピアスをつけてる奴を、一番真面目に働きそうだ、なんて思うひとだ…。信じられん…。
族の特攻隊長!? 女のヒモ!? 店の女の子がタレントのたまご!?
どれもこれも信じられん!!
「オレさ…、村井くらいの弟いるんだよ。今大学生なんだけど。だからお前弟みたいでさ…」
「……。年、随分離れてますよね…?」
「腹違いなんだよ。親父はオレが物心つく前に亡くなってさ、それから中学んときに母親が子連れの男と再婚して。そんときは再婚した母親が許せなくてさ……。さんざん迷惑かけて……。ひどかったよ、ほんと。族の連中が家来てシンナーやったり<中略>弟ちっちゃかったしさ、母親と義理の親父には本当に迷惑かけた。その義理の親父さ、俺が東京来てから病気になって、ずっと入退院繰り返してたから母親も働きだしてさ。俺はママから金借りたりしながら、弟の学費とか生活費仕送りしてたんだよ」
中学二年までサンタクロースを信じていたぼくには考えられない人生だ……。
気が付くと、ぼくは野村さんの話になんの疑いも持たず、目をうるうるさせて聞き入っていた。
「今年さ、弟、大学決まったんだよ。俺すげー嬉しくてさ…。最近彼女出来たんだと」
そして唐突に
「村井はロック好き?日本のバンド聴く?」
「あんまりCDとか持ってないっすけど、興味あります…」
「お前フリクションとかミラーズとか知ってるか?俺が中学んときだな、すげー聴いてたよ、先輩の影響で。東京ロッカーズって聞いたことねえか…。ねえよな…。めちゃめちゃかっこいいぞ。懐かしいな…。もう随分前だよ。今度貸してやるよ。俺も何年も聴いてねえけどさ、なんか聴きたくなってきたよ。今度俺ん家来いよ」
そう言って、野村さんはアイスコーヒーをおかわりした。ぼくはお店のカウンターにあるパネルに書かれた「本日のストレートコーヒー/ブラジル」を注文し、氷が溶けて薄くなったアイスコーヒーを一気に飲んだ。
「お前、ママんとこでずっとやっていけそうか!?」
「ずっとは……」
「2ヶ月働けば給料は上がるしさ。なんかつらいことあるか!? 客商売なんてどこも大変だけどさ、ママの店の客はみんな喜んで帰ってくだろ!? やりがいあんだよ、あの店は。大変だなんて思ったことねえな、俺は。ボンボンのブタみてえなぼっちゃんが来てもさ、店で楽しんでるの見ると俺らは嬉しくなるじゃん」
「はい……」
「ただお前彼女いねえからって店の女の子にはほんとに手出すなよ」
「……」
「どんくらいいねえの?」
自分一度もいたことねっす!!!!
「……1年くらいす」
「そっか。じゃぁ、たまってるよな、今度いいとこ連れてってやる!! すげーぞ、お前。」
嫌ですっ!!
風俗では駄目なんですっ!!
ぼくは大事な大事な彼女で童貞を捨てるって決めてるんですっ!!!!
「はいっ!! ぜひっ!!」
「そういえばさ、お前この前厨房で皿割っただろ!?」
「……はい!?」
「カルロス、すげー怒ってたぞ。別に言う必要ねえけど、一応、教えとくわ…。村井、誰にも言わねえか?」
「……」
野村さんは、お店の厨房を仕切る南米出身のカルロスの秘密を小声で話しだした。
「あいつさ、どういう経緯でママの店で働き出したか俺も知らねえけどさ…。実はさ、あいつ……」
「……」
「人、殺してんだよ。南米のどっかの国で。詳細は謎だ。で日本に逃げてきたらしくてさ…。あいつ、すぐキレるだろ!? 血、濃そうだもんな……。」
血が濃いかどうかはわからないが、確かにカルロスがちょっとしたことですぐキレることは、ウェイターの間では知れた話だった。
特に、彼の持ち場で何かしでかすと尋常じゃなく怒る。
数日前に一度、丁寧に盛り付けられたチーズ&サラミをカルロスから受けとる際に手を滑らせ、床に皿ごと落としてしまった。厨房の床に皿の破片と、チーズやサラミが飛び散った。
「すいませんでしたっ!!」
慌てて片付けようとすると、
「ナーカー二ーハイルナー!!!!」
と大声で叫び、ひたすら謝るぼくに耳元で
「コンドヤッタラコロス」
と静かに囁いた。
バイト先の些細な失敗談として記憶から消えつつあった出来事が、戦慄とともに鮮明に蘇った。
ぞっとした……。
まさか彼が殺人犯だなんて……。
いやいやまさかそんなこと信じられるわけがない。
第一そんなことして日本に逃げられるわけがない。
ぼくの頭は厨房に潜む死神のことでいっぱいで、すっかりコーヒーを飲むのを忘れていた。
野村さんは、「そろそろ店に戻らないと」と言い、さっと席を立って会計をしに行った。ぼくはミルクと砂糖がたっぷり入った冷めたブラジルを一口だけ口に入れると野村さんの後に続いた。
その小さいカップに入ったコーヒーが一杯1,100円、アイスコーヒーが1,000円という値段を初めから知っていたら、ぼくは追加注文なんかしなかっただろう。お礼を言ったあと、値段も見ずに注文したことを謝ると、野村さんは「やっぱ銀座は高いよ」とだけ言った。
ある日、寮の玄関で尾花沢産スイカを落とした“事件”と時を同じくして、ぼくはママさんのお店で何度目かのミスを犯した。
……よりによって死神の厨房でだ。
ぼくは色鮮やかなフルーツが盛り合わされた皿を、またしても彼の大事な作品を床に落としてしまったのだ。
厨房の近くにいたママさんがゆっくりと入ってきて、「注意力が散漫してるからよっ!!」とぼくを叱った。
ママさんがぼくを叱っている間、別の皿に丁寧にフルーツを盛り合わせているカルロス。自分のテリトリーで皿を二度も割られ、心を込めて作った作品を一瞬にして粉々にされた彼は、今にも噴火しそうな怒りを抑えながら手際よく二度目のフルーツの盛り合わせを作った。
ぼくは、二作品目のそれをカルロスから受けとってから、フロアのテーブルに置ききるまで全神経をその作品に集中させた。
無事に任務を遂行し終えたところで改めてカルロスに謝罪に行った。
厨房に入ってすぐにぼくは体が固まった。
なんと包丁を真っ直ぐぼくに向けた死神が鋭い目をして、待ってましたとばかりに立っていたのだ。
左手に持っていたトレイが床に激しい音をたてて落ちた。
言葉が出ない……。
野村さんの話を思い出した。
反射的に命請いをするため土下座をしようと体を曲げた瞬間、カルロスが中腰で半歩前に出た。
「イイカゲンオマエコロス!!!!」
殺されるぅー!!!!
ぼくはトレイを拾うことも忘れて厨房を出た。
数日後、ぼくはお店に電話し、野村さんに「一身上の都合で」辞めることを伝えた。
ぼくは野村さんから風俗へ連れて行ってもらうことも、東京ロッカーズと呼ばれるバンドのレコードを借りることもなく、僅か2ヶ月でママさんのお店を辞めた。
女神たちに彩られた華やかな夜の銀座は、真っ赤な液体を流し、白目をむいた金髪青年が高級クラブの厨房に転がる血なまぐさい危険な夜の街へと変貌し、ぼくの脳に刻まれた。
ぼくは『狂い咲きサンダーロード』を観るたびに、顔も声も山田辰夫さんそっくりの野村さんを思い出した。
 村井 守
村井 守1978年1月15日生まれ。
やぎ座。O型。山形県山形市出身。中学生の頃のあだ名は「ゴボウくん」。
バンド「銀杏BOYZ」元ドラム担当。

