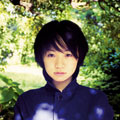2008.02.29
vol.7「デストロイ」

真夏の東京は嫌になるほど蒸し暑い。山形の夏も、いやどこにいたって夏は暑いに決まっているが、山形にいたときは日陰に入れば涼しい風が直射日光に照らされたほてった皮膚を冷やしてくれた。
東京には信じられないほどたくさんの巨大なビルがひしめき合ってそびえ立ち、どこを歩いてもすぐに日陰がある。ところが日陰に 入っても暑さは変わらない。風がない。ちっとも涼しくない。どこにいたってムンムンムンムンしていて気分が悪くなる。
寮に帰ってみねたに貰ったミックステープを聴こう。
クーラーをガンガンにつけた寮の二階にあるぼくの四畳半の部屋は、外の暑さが少し懐かしく感じるほどひんやりとしていた。
クーラーの設定温度を極端に下げ、風量も強くしていたために、テープを聴き終えるころにはTシャツ一枚では耐えられないくらい肌寒くなっていた。けれどぼくはクーラーの設定温度を調節するようなことはせず、窓を開け、ムンムンした真夏の東京の空気を入れて部屋を適度な温度に調節した。
外を眺める。
向かいのたいそう大きな家のこれまた広大な庭にある無数の木々から聴こえてくるたくさんの夏の音。姿こそ見えないが、恐ろしいほどの数の蝉が木々にとまっていることがわかる。
よく見ると寮とこの大金持ちの大きな家の境にある高い塀の上に張られた有刺鉄線に一匹の蝉がじっとしがみつき、今まさに鳴かんとしている。
じーーーーーー
抑揚のない音。途中で鳴きやんだかと思うとまた一定のテンションを保ちながら鳴き始める。ぼくがタバコの吸い殻をそいつに向かって投げると、飛び立つと同時に一瞬、ビンッと強く鳴いてあっという間に空の中に消えていった。
自分の存在をかけた強烈な鳴き声。聞いているこっちの気が狂ってしまうほどだ。
雄は鳴いて雌を誘う。
幼虫の地中生活が、成虫の野外生活に比べて何十倍も長い蝉の鳴き声は、生に対する喜びの唄なのか、死に対する恐れの唄なのか……。それともその両方か……。
セックスへの期待なのか、セックスへの焦りなのか…。期待するから焦るのか……。
そういうことを考えるほど余裕があるぼくの部屋の温度の心地よさ。
窓なんて開けなくてもクーラーを止めればいいだけの話なんだけど、電気代込みの家賃だったから寮の管理人のおじさんへのあてつけもあり、省エネとは真逆のことをしていた。
1ヶ月と半月の長い長い夏休みに入ってから、ぼくはすぐに髪を脱色した。
ぼくは東京での初めての夏を迎え、浮かれたことをしたかった。山や川や海に行くなんてことはもうこりごりだった。山形にいたころ散々ネイチャードライブには行っていたし(家族と)、ぼくが望んでいたのは夏の虫の鳴き声で目覚める田舎の夏ではなく、ネオンきらめく都会の夏の夜のほうだった。
夏だもん。夏の東京の夜だもん。おれ若いし、何かあるべー。
まずは、念願の金髪だぁー。
週の半分は夜勤の日雇いバイトをしていたため寮で夕食を食べる回数が減り、この夏にはほとんど寮の食堂に行かなくなったぼくにただでさえ目をつけていた管理人のおじさんは、金髪になったぼく を見て廊下ですれ違う度にますます嫌な顔をするようになった。
朝帰りをし、玄関の掃除をしている管理人のおじさんとばったり会うと、「山形のお父さんとお母さんはどう思うだろうね……」と言った。
この頃の朝帰りはバイトだけでなく、ライヴへ行き、その後朝までファミレスで時間をつぶして帰るパターンもあった。
夏休みということもあり、ぼくは千葉に住むみねたとライヴハウスへ通いつめた。
渋谷ギグアンティックや下北沢シェルター、屋根裏、西荻窪ワッツや新宿ジャム、ロフト、アンチノック、高円寺20000V、恵比寿ミルク……。
暗くて狭いライヴハウスに入ると、タバコの匂いと壁に染みついた汗の匂いが、ほこりと一緒に何日も寮の共同風呂に入ってないぼくの体にまとわりつき、体臭をいっそう濃くした。
開演の時間が近づくと、ぼくとみねたは何もしゃべらず別々に客席の一番前へ行き、バンドが登場するのを固唾を飲んで待った。
バンドが登場し、演奏が始まると全身で音を浴び、無我夢中で音に飛び込んだ。
演奏が終わると、汗でぐちょぐちょになったズボンを引きずり、ドリンクバーへ行ってコーラをオーダーすると、隣には必ずぼく以上に汗だくになったみねたが既にコーラを飲み終えて立っていた。
そしてまたバンドが登場すると別々に一番前へ行った。
どのバンドも音がデカい。足の先まで血管がどくどくいって、股間がぞくぞくする。音の違いなんてわからず、どのバンドも全身で聴いて好きかどうかで体を動かした。
ライヴが終了し会場を出ると、出口の階段にはさっきまで演奏していた出演者が額の汗をふく間もなく次のライヴのフライヤーを配っている。配っているのは出演した人の他にも、さっきまで中でライヴを観ていた人、フライヤーだけを配りに来た人もいる。そのため出口の階段の両脇からフライヤーを持った手がずらっーと伸びており、客はそのフライヤーを一枚一枚企画者本人からもらって一列になって階段を降りていく。
フライヤーをもらうときに、客は出演者に声をかけ、また出演者は顔なじみの客に声をかけた。ぼくも出演者と話がしたくてしょうがなかったが「ヤバかったっす…」ただこの一言を言うことが精一杯だった。
顔なじみの客は、ライヴの感想や、さらに突っ込んで今注目してるバンドや来日する予定の海外のバンドのことなどを話し、互いに情報交換していた。
こんな調子のため、ライヴが終わってもライヴハウスを出るまでにはかなりの時間がかかった。だがこの時間が、それまで脳をぐちゃぐちゃに叩きのめされ、血が沸騰しきってハイになった状態からゆっくりと現実の自分を取り戻し、ライヴの余韻に浸れるちょうどいい長さだった。
出演者や、企画者の中にはTシャツやステッカー、布パッチや缶バッチなどの物販の他にファンジンを作って売っている人もいた。
ぼくはそういうファンジンをかたっぱしから読み、そこで紹介されるバンドのレコードを探した。
夜勤のバイト明けにもらう一日分の給料を、吉野家の牛丼分を差し引き全額レコードにつぎ込んだ。
ライヴに行くときはライヴハウスがあるその街のレコード屋へ行って買い物をし、そのお店のビニール袋片手にライヴハウスへ向かい、帰りはそのビニール袋の中に貰ったフライヤーやファンジンをぎっしり詰め込んだ。
インターネットが今ほど普及してない時代に、会場で売られるファンジンは貴重な情報源だったし、フライヤーはデザイン自体が重要な情報源だった。
フライヤーにはホームページのアドレスの代わりに企画者の住所と電話番号が記載されていたので、企画者に直接電話してチケットを取り置きしてもらうこともあった。
ぼくとみねたは、ライヴハウスを出た後、すぐにもらったばかりのフライヤーを見て次に行くライヴの相談をした。ぼくはこのミーティングがたまらなく好きだった。
濡れたTシャツから汗が白い煙となって蒸発している間に、自販機でジュースを買い、タバコに火をつけ、ライヴの興奮覚めやらぬまま、写真をコラージュしてるものやイラストの描かれたフライヤーを見て次に行く来週のライヴを決めた。
ぼくらはレコード屋かライヴハウスに直接集合した。お互い携帯はなかったので時間に遅れるときはどちらかが公衆電話からアパートへ電話した。千葉と東京という距離なので、たいがいがもう家を出たあとで留守になっていたが、それでもライヴが始まった頃にはお互いステージの前に立っていた。
ぼくにとって、これらのライヴは次の一週間を生き抜くために必要なハイで純度の高い薬になっていた。
この頃には、寮でも話しを出来る友達が出来ていた。
隣の部屋のシンちゃんは、この夏に始めて学校が一緒だということが発覚した。愛媛出身のシンちゃんは絵画科で、ぼくはデザイン科。ぼくの方では学校でシンちゃんを見かけたことはなかったが、シンちゃんの方では前から同じ寮に住むぼくに気づいていたという。
そして共同風呂でシャンプーを貸してくれたヒロシくん。
千葉から出てきたヒロシくんはお茶の水にある専門学校に通っていた。
このふたりと知り合ってからはぼくは以前より寮の食堂に行くようになり、共同風呂にも入るようになった。
シンちゃんもぼくと同じように故郷の訛りがとれないでいた。ヒロシくんはぼくらふたりの北と南の違った訛りを面白がって聞いていた。
ぼく以外のふたりも部屋のクーラーは一日中つけっぱなし。三人が集まるとテレビゲームをしながら、寮の管理人の話で大いに盛り上がった。
窓を開けると声がもれるため、窓は締め切り、三人ともスウェットを着ながらゲームをした。そこまでしてもクーラーを止めようとしなかったから8月の寮の電気代は相当な額になったと思う。
シンちゃんは部屋にゴキブリが出るとぼくを呼び、ぼくはゴキブリを駆除するのとかわりにアダルトビデオをシンちゃんから借りた。
そしてヒロシくんは高校からスケボーをやっていたが、まだ寮に来てから一度も使っていない新しい板に乗りたがっており、一緒にスケボーをやる仲間を探していた。ぼくはヒロシくんの今は使っていない使い古しの板を借り、ふたりで武蔵境の北口を出て左にあるスーパーの駐車場でひとけのない夜からスケボーを始めた。
全くの初心者で転ばないように両足で板に立っているのがやっとで、オーリーも何も出来たもんじゃないが、転倒必至で左足を板に乗せ、右足で思い切り地を蹴ってスピードを出すと、バック・トゥ・ザ・フューチャー2のマーティみたいな気分になり、地面すれすれのところを宙に浮かんで飛んでいるようで気持ち良かった。
ヒロシくんはしきりにトリックの練習をしていたが、少しずつ板に乗れるようになるぼくを観て喜んでいた。
ぼくらは門限の11時を過ぎても帰らなかった。
というのも、ヒロシくんは門限を過ぎても部屋に無事帰還することができる限られたひとなのだ。
塀と有刺鉄線に囲まれたこの寮に入るには、正門の錆び付いた門扉を通り、玄関で暗証番号を入力しなければドアは開かない。門限の時間になると管理人は門扉と玄関ドアに鍵をかける。門限を過ぎたら第二の関門である玄関ドアはもちろんの こと、第一の関門である門扉も絶対に通れない。
しかし、ヒロシくんは誰もが見過ごしている、ほとんど使われていない管理人用の通用口があることを知っており、さらにその通用口用の門扉の鍵が壊れていることを知っていた。ぼくらは正門を通り過ぎたところにある第一の関門を通り、塀の中へなんなく入り建物の裏側へ回った。途中、灯りの消えた管理人の窓の下を息を殺して通る。
裏側へ回りきって、いくつもの窓の下をしゃがみながら通り過ぎ、ヒロシくんの部屋の窓から何食わぬ顔をして寮に入ることが出来た。
ぼくはヒロシくんが一階の部屋に住んでいることに感謝し、きみは本物のトリックスターだ!!と、ヒロシくんを讃えた。
ぼく以外にもこの窓を利用しているらしいことは、窓のすぐ下にあるヒロシくんの真っ白いベッドの上に刻印された様々な形の靴底の跡を見れば明らかだった。
それからはライヴやバイトで門限を過ぎて帰っても一箱のタバコと引き換えにヒロシくんの部屋から寮に入ることが出来た。
都内でライヴを観てきたみねたが、ヒロシくんの部屋を通りぼくの部屋に泊まりに来ることもあった。ときには門限をとっくに過ぎたあとでみねたとヒロシくんとぼくとでヒロシくんの部屋から寮を抜け出し、駅前に行って三人でスケボーをしたこともあった。
夏休みのある日、めったに鳴らないぼくの部屋の電話が鳴った。夏休みなのに山形に帰ってこないぼくを心配してかけてきた母親からの電話だと思ったが、受話器から聞こえたのは身に覚えのない若い女性の声だった。
急にぼくの手が震えだした。
同じ学校のモモちゃんだった。
どうしてぼくに……!!!?
わけがわからなかった。
「もしもし。ムラッチですか!? モモです。ムラッチですか!? ムラッチ!?」
疑問と興奮と恐怖が一気にぼくの人格を変えた。
「ぬおおー!!!!!! なによモモちゃん、どうしたのー!!!?」
「いつCD返してくれるの? ムラッチさ、夏休み前に返すって言ったじゃん……。夏休み明けでもいいんだけどさ……。」
モモちゃんは少し苛立っているようだった。
ぼくはモモちゃんとタクちゃんと行ったあの渋谷でのライヴの数日後にモモちゃんからたくさんのCDを借りていた。
X、アヴェンジャーズ、リアルキッズ、スティッフ リトル フィンガーズ、ティーンジェネレイトやメジャーアクシデント、コックニーリジェクツ等々……。
確かにぼくはそれらのCDを夏休み前には返すから、と約束して借りていた。
忘れていた……。
それにモモちゃんにぼくの寮の電話番号を教えていることもすっかり忘れていた。
モモちゃんは、来週都内に行くからそのときにどこかで待ち合わせしようと言ったが、思いがけずかかってきたモモちゃんの電話に興奮したぼくは衝動的に会いたくなり、「明日そっちのほうに行く用事あるし」と言い、明日の夕方、彼女の住む川越までCDを返しに行くことを約束して電話を切った。
電話を切るころにはモモちゃんは「無理しなくてもいいのに」とぼくの嘘を見透かして笑っていた。
受話器から聞こえた切る直前の「バイバイ」がどこからこんな声が出るんだろうというぐらいきれいで艶があり、その一言がいつまでも耳から離れなかった。
モモちゃんと学校以外で会うのはタクちゃんと三人で行ったライヴ以来だから二度目だ。
でも今度はふたりっきり。
ぼくはネオンきらめく都会の夏の夜の下で二十歳前の男女が繰り広げる様々なことを想像して眠った。
次の日の昼、ヒロシくんからのスケボーの誘いを断りぼくは意を決して寮を出た。
ぼくは高円寺の古着屋を駆け足で回り、白と黒のボーダーのガーゼシャツとぼろぼろになったGパン、それにほこりを被った真っ黒いラバーソールの革靴を買った。
約束の夕方までにはまだ時間がある。
ぼくは高円寺の駅前にある喫茶店へ入って窓側の席に座り、ブレンドコーヒーを注文した。
大きな大きな窓。
ぼくは高円寺の北口の風景を見ながら頭の中でモモちゃんと会ったときの会話をシュミレーションした。
暖かいブレンドコーヒーが運ばれてくる。
香り高い湯気が次から次へと昇っては宙に消えた。
なんともいえない幸福感に浸りながら少しずつコーヒーをすすった。
コーヒーを飲みほしたあと、ぼくはその喫茶店のトイレに入り、買ったばかりの洋服に着替えた。金髪だったこともあって鏡でみるパンクファッションに身を包んだぼくはなかなか様になって見えた。
……いや。
……。
!!!!!!
なにか違う!!
体型がきゃしゃなせいかいまいち迫力がない!!
服に着させられているぞ!!
何かが足りない……。
リアリティが足りないっ!!!!
ぼくはそそくさと420円を支払い会計を済ませ、純情商店街にある薬局に入り、包帯と、手と手首用のサポーターを買った。
そして足早に高円寺駅の公衆トイレにもぐりこみ、ボーダーのガーゼシャツを靴で何度も何度も踏みつけたり、床に垂らした水を染み込ませたりした。
最後に手と手首にサポーターをそれぞれつけ、首から包帯を巻いて腕を固定した。
もともとぼろぼろのシャツがさらにぼろぼろになり、ところどころから肌が見え隠れして公衆トイレの床の汚れも加わり、若いホームレスのひとになったかのようだった。
しかし、トイレの鏡に写った包帯をしているぼくは、いままさに喧嘩を終えたばかりの危険な男にも見えた。
電車の中で視線を感じるときもあったが、こういう人目につく格好をしていると不思議と自分が本当に危険な男に思えてきた。
デーストロッーーーイ!!!!!!
いやいや……そんなこと言ってる場合じゃない……。
ぼくの頭の中はモモちゃんのことでいっぱいなんだ。
落ち着け……。
あっという間に約束の時間に川越駅へ着いた。
階段を登り、待ち合わせ場所の改札へと向かう。
緊張がマックスまできていた。
すぐに改札の向こう側にいるモちゃんを発見した。
……。
口から泡が出そうになった。
学校で見るモモちゃんも強烈だが、こうやって日常の世界にぽつんと立っている彼女はより強烈で可愛いかった。
モモちゃんはこちらを見たが、金髪になったぼくに気がつかず、彼女の視線はぼくを通り過ぎて改札を行き交う人々を追っていた。
モモちゃんに近づきながら、彼女だけにピントを合わせたぼくの目は、彼女を囲む周囲の風景をピンぼけさせて何度も何度もシャッターをきり、脳に光を焼き付け時間を切り取った。
目の前まで行ったところで、やっとぼくに気がついたモモちゃんは一瞬びっくりしてとっさに体をのけぞらせ、それからぼくの挨拶も聞かずに足元から頭のてっぺんまでまじまじとぼくを眺め、ちょっと間をおいて笑いだした。
モモちゃんの笑いは止まらず、その笑い声はだんだん大きくなり、そのうちぼくもつられて笑いだした。
笑いながらモモちゃんが
「それなに!?」と聞く。
「なにが!?」
「だからなによそれ……ぷっ……」「……。」
そしてまたお互い笑った。
「ぷっ…その腕どうしたのよ!?」
「……高円寺のバンドマンと喧嘩して……ぷっ……。」
「ぷっ……キャハハハハハ……」
川越駅の改札を境にあちら側とこちら側でふたりで大声を出して笑った。笑いすぎてしまいには涙まで出てきた。
結局ぼくは改札を通らずに笑いながらCDを返し、モモちゃんも笑いながらそれを受け取って会話という会話もせずに別れた。
階段を下り、プラットホームに足を降ろしたときに、やっと笑いは止まったが、電車に乗っても目から溢れ出る涙は止まらなかった。
数日後、ぼくは髪を黒く染め、東京の白い煙をかき分けながら物凄いスピードで走る山形新幹線に乗り、建物が密集した街から田んぼや山や川へ移り変わる景色をぼんやり眺めながら山形へ帰った。
そして実家の畳にだらっと寝そべって、夏の虫の鳴き声を静かに聞きながら残り少ない夏休みを過ごした。
 村井 守
村井 守1978年1月15日生まれ。
やぎ座。O型。山形県山形市出身。中学生の頃のあだ名は「ゴボウくん」。
バンド「銀杏BOYZ」元ドラム担当。